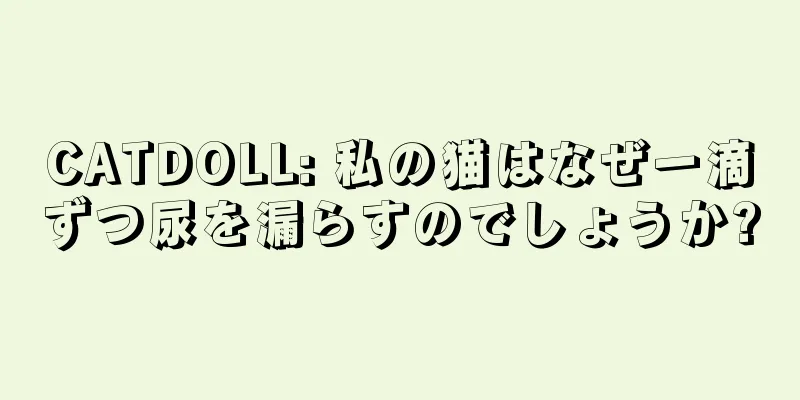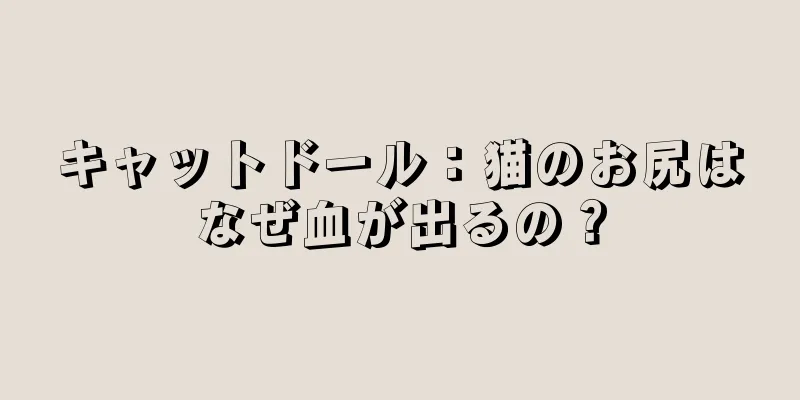猫は発情期、泌尿器系のトラブル、水分摂取不足などにより尿漏れを起こすことがあります。このような場合、飼い主は猫の排尿に注意する必要があります。猫に排尿運動があるのに、排尿回数が増えた場合は発情期ではないかと考えられます。猫が尿漏れをしていて、さらに頻尿、血尿、排尿困難、排尿困難、尿漏れ、尿漏れなどの症状を伴う場合は、尿道炎、膀胱炎、尿道結石、膀胱結石など、泌尿器系の病気である可能性があり、できるだけ早くペット病院に行って検査と治療を受ける必要があります。
1. 発情期
猫に排尿運動があるのに、排尿回数が増えた場合は発情期ではないかと考えられます。
1. 発情期の猫は、無作為に排尿したり、遠吠えをしたりすることで、異性の猫を引き付けることがあります。飼い主は、発情期前に雄猫が叫び続ける、雌猫がお尻を突き出すのが好きななど、猫が他の発情反応を示すかどうかに注意する必要があります。
2. この場合、飼い主が猫に子孫を残させたいのであれば、交尾相手として異性の猫を探すことができます。飼い主が猫に子孫を残す予定がない場合は、発情期が終わった後に近くの病院に連れて行き、不妊手術を受けることができます。
3. さらに、発情期には猫が家から逃げ出すこともあります。飼い主は常に猫の意図に注意を払い、事故を避けるためにドアや窓を閉めることをお勧めします。
2. 泌尿器系の問題
猫が尿を漏らしていて、さらに頻尿、血尿、排尿困難、排尿困難、尿漏れ、尿漏れなどの症状を伴う場合は、尿道炎、膀胱炎、尿道結石、膀胱結石などの泌尿器系の問題の可能性があります。
1. まず、尿道炎、膀胱炎などの感染症を検討してください。炎症が関連する粘膜に継続的に影響を及ぼし、猫の頻尿、尿を我慢できない、血尿、膿尿などの症状を引き起こします。猫は通常、トイレの中で何度もしゃがみ込み、同時に遠吠えしますが、これは排尿の痛みによって引き起こされます。
2. 次に、尿道結石、膀胱結石などの結石疾患を検討します。結石は尿路の粘膜に影響を与えるため、猫は頻繁に排尿したいという衝動を感じ、尿を我慢できないという症状も現れます。
3. さらに、結石が尿道や膀胱の出口を完全に塞ぐと、尿閉を引き起こし、非常に有害で、膀胱破裂、急性腎不全などの病気につながる可能性があります。
4. 猫が泌尿器系に問題があると疑われる場合は、飼い主はすぐに猫を近くのペット病院に連れて行き、検査を受けることをお勧めします。 X 線検査、尿検査、血液定期検査、生化学検査などを通じて、猫の泌尿器系の具体的な状態を確認し、具体的な状況に応じて対応する治療措置を講じることができます。
3. 水を飲む量を減らす
1. 猫が水を飲むのを嫌い、毎日の食事に含まれる水分が少ない場合、猫は尿を少なく生成するため、排尿の回数が少なくなり、数滴の尿しか出なくなります。
2. この場合、飼い主は猫にもっと水を飲むように指導する必要があります。猫の水分補給のために、適量のウェットフードや、水分を多めに含んだ缶詰のフード、果物や野菜を与えることもできます。十分な水分を吸収すると尿の量が多くなり、猫は正常に排尿できるようになります。