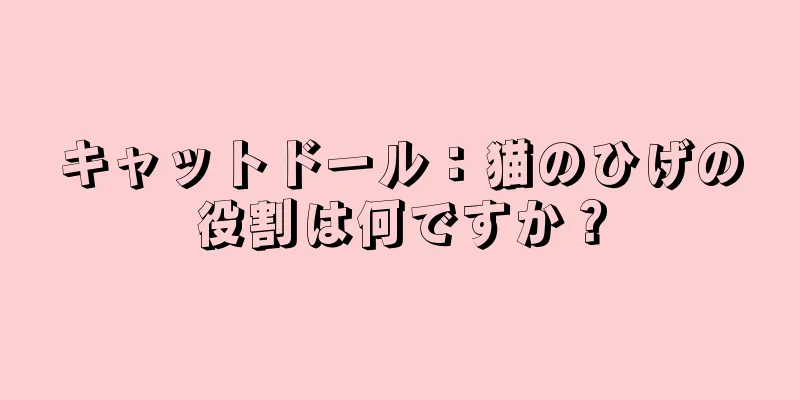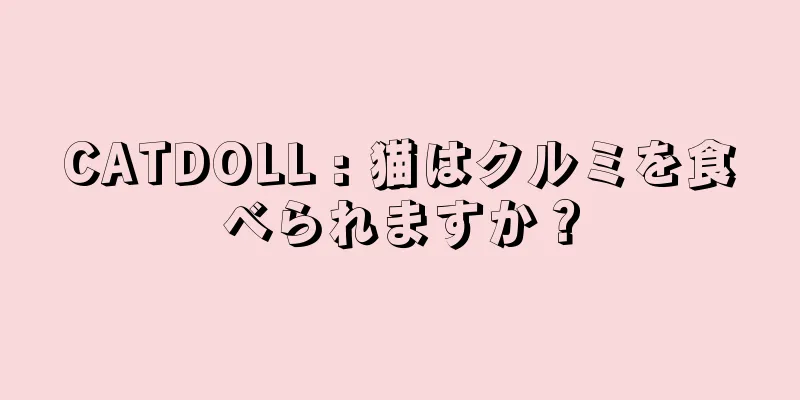子どもの啓蒙教育では小動物に関する科学的な普及活動が盛んに行われている。その中に、誰もが幼い頃に聞いたことがあるであろう猫に関する言葉があります。つまり、猫のひげの長さは頭の片側の幅と同じ長さです。猫がネズミの穴を掘るとき、ひげを使って穴の幅を測り、頭が入るかどうかを確認します。頭が入る場合は、体全体も入ります。皆さんは聞いたことがありますか?
これは、私たちが大人になるとめったに聞かなくなる話です。なぜなら、猫のひげは必ずしも頭や肩の幅と同じではないし、猫の頭は穴を通った後、穴に引っかかって抜けなくなることがよくあるからです。ヒゲの幅は測れないのでしょうか?なぜこれが私たちが子供の頃に聞いたものと違うのでしょうか?私たちが幼い頃に聞いたニュースがすべて嘘である可能性はあるでしょうか?
実際、このちょっとした科学的な話にはある程度の真実が含まれていますが、猫のひげには非常に複雑な機能があるため、完全に正確というわけではありません。機能の 1 つは、物体に触れることで情報を収集し、幅を測定できるようにすることです。しかし、猫は一般的に、ひげに頼って穴の幅を正確に測ることはありません。これは実は、猫が狭い隙間に穴をあけているのをよく見る人たちの推測です。それは理にかなっていますが、現実には明らかではありません。
猫の種類によっては、頭や肩の幅よりもはるかに長いひげを持つ猫もいれば、非常に短いひげを持つ猫もいます。また、無毛猫のようにひげがほとんどない猫もいます。また、猫の中にはまっすぐなひげを持つ猫もいれば、カールしたひげを持つ猫もいます。では、猫のひげの具体的な機能は何でしょうか?
まず、猫のひげは毛の一種であり、猫には一般的に3種類の毛があります。 1 つ目はガードヘアで、首、背中、手足、尾などに分布しています。もう 1 つは絨毛で、頭、顔、手足の内側、腹部などに分布しています。3 つ目は触覚毛で、目の上、鼻の両側、肉球の間、耳の内側などにあります。鼻の両側にある触覚毛はひげです。目の上には、眉毛のような長い触覚毛が数本あります。耳の内側にも長い触覚毛があります。足裏の間にも触覚毛があり、一般的に足毛または足底毛と呼ばれます。
名前が示すように、触覚毛の機能は周囲の環境にある物と接触することです。一般的に、触感毛の質感は比較的柔軟で硬いです。この構造により、毛先に触れると毛根まで正確に情報が伝わり、猫は収集した情報を分析できるようになります。猫の耳や足の裏にある触覚毛は、ひげほど硬くありません。これは、足の裏が接触する空気と地面の振動をより繊細に感知する機能があるためです。そのため、特に猫の肉球の間の毛は、ひげよりも柔らかくて細いのです。しかし、飼い主が注意深く観察すると、猫の肉球の間の触感毛の質感が、足指の裏側の毛羽の質感とは異なることがわかります。
猫のひげについて話しましょう。その主な機能は、特に暗い夜間に触覚を通じて環境情報を収集することです。猫はある程度の夜間視力を持っていますが、ひげは周囲の環境を感知するのに役立ち、盲人にとっての杖の役割を果たします。猫のひげの先には固有受容器と呼ばれる一種の感知装置があり、触覚に基づいて物体の質感、強度、距離に関する情報を収集し、刺激信号を神経インパルスに変換して神経中枢に送信し、現在の環境の変化を分析することができます。
猫のひげは環境の変化にどの程度敏感なのでしょうか?時には、猫のひげは、物理的に接触することなく、空気の流れのわずかな変化さえも捉えることができます。つまり、猫のひげは「聞く」役割も果たすのです。猫の毛の種類の中でも、耳介の内側の毛がこの機能に最も敏感です。猫の耳の内側と耳介の上部にある毛の房は、音によって伝えられる空気の振動を捉えることができ、猫が音の発生源と原因を分析するのに役立ちます。ひげでもこの効果は得られますが、耳の周りの毛ほど敏感ではありません。
猫のひげの測定機能に関して言えば、その最大の用途は、猫が通り抜けられるかどうかの穴の幅を測るのではなく、動的な距離の変化と空気の流れに基づいて、前方の障害物と猫自身の距離を測ることです。ある人が猫のひげを切る実験をしたところ、猫が動くときにつまずいたり、自力では通り抜けられない穴に潜り込んだりするのを観察しました。そこで研究者たちは、猫のひげを使って穴の幅を測ることができると結論付けました。しかし、この実験が実際に示しているのは、猫はひげがないことにしばらくは慣れることができず、以前ほど効果的かつ正確に環境を感知できず、そのために物にぶつかったり穴を掘ったりするということなのです。ヒゲなしで生まれた無毛猫は、子供の頃からヒゲに慣れているため、一生あちこち走り回ることはありません。
多くの猫の飼い主は、猫が遊んでいるときに、口の周りの肉が膨らみ、ひげの先端が前方に動くことに気づいています。これは私が今言ったことを裏付けるものです。猫は、何かに触れようとすると、ひげを周囲の空気や物体と接触させて情報収集するため、遊ぶときにひげを前に向けます。猫は、食べたり飲んだりするときに、ひげがゴミや水滴で汚れて知覚が低下するのを防ぐために、ひげを後ろに、時には顔の近くに動かします。
猫の飼い主は、指で猫のひげを触って、ちょっとした実験をすることができます。指がひげに触れたばかりのとき、またはまだ触れていないとき、こちら側のひげは猫の制御下で後ろに向き、反対側も同様に向きます。これは猫がひげを守ろうとする敏感さです。猫は、ひげを引っ張られたいのか、それとも何か他のことをしたいのか分からないからです。