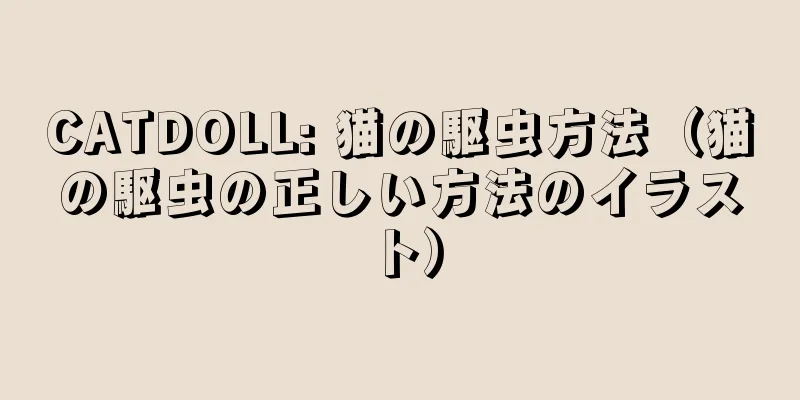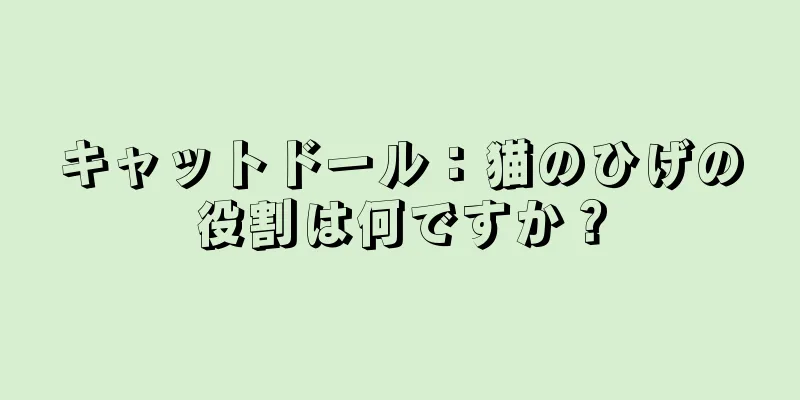ペットの飼い主は、ペットの外部駆虫を行う際には細心の注意を払い、薬の使用説明書をよく読む必要があります。薬は猫の頭と首の後ろ、つまり猫の首の後ろの肩甲骨の間に滴下します。猫の首の後ろの毛を手で引っ張ることができます。猫の皮膚や肉が露出したら、先ほど抜いた毛を指で押さえながら薬を垂らします。滴下中は、髪の毛を握っている手を離さないでください。
薬を塗った後は、猫を慌てて逃がさないでください。代わりに、静かに観察して薬が猫の皮脂腺に浸透するのを待ち、その後、猫が毛を整えて自由に動けるように手伝ってください。あるいは、飼い主が心配な場合は、猫にエリザベスカラーを付けることもできます。
それでも飼い主が適切に対処せず、猫が駆虫薬を舐めてしまい、冒頭のような場面が起こった場合は、インターネットで緑豆水や砂糖水などの「民間療法」を愚かにも試さないでください。すぐに猫を病院に連れて行き、医師にどのブランドの駆虫薬を使用しているか、どのくらいの量を使用しているか、猫がどのくらい舐めているか、どのような症状があるのかを伝えてください。そうすれば、医師はすぐに治療計画を立てることができます。
実際、猫を家に連れてきたら、健康のために定期的に内部と外部の駆虫を行うのが普通です。しかし、多くの猫の飼い主は、猫は何歳になったら駆虫を始めるべきかなど、駆虫について多くの疑問を抱いています。駆虫はどのくらいの頻度で行う必要がありますか?どんな駆虫薬が良いのかなどなど。そこで今日は一気に虫を駆除する方法を紹介します~
まず、駆虫について話す前に、猫の体にどのような寄生虫が影響を及ぼし、どのような害を引き起こすのかを知る必要があります。
猫の体外の寄生虫には、疥癬、ニキビダニ、ノミ、シラミ、耳ダニなどがあります。体内の寄生虫には、条虫、回虫、鉤虫、コクシジウム、トリコモナス、ジアルジア、フィラリア、回虫などがあります。これらの寄生虫の危険性は何ですか?まず、いくつかの外部寄生虫の危険性を見てみましょう。
疥癬:疥癬ダニは通常、猫の外耳道に発生します。猫が疥癬ダニに感染すると、激しいかゆみ、脱毛、皮膚の赤みなどの症状が徐々に現れます。症状が徐々に悪化すると、疥癬ダニが猫の角質層の表面に穴を開け、猫の皮膚表面に密集した小さな丘疹、フケ、紅斑が現れ、徐々に厚いかさぶたが形成されます。
デモデックス: 猫のデモデックスは通常、猫の目、耳、唇、前脚の内側の毛のない部分に発生します。境界がはっきりした比較的小さな紅斑性病変が 1 ~ 5 個あります。この寄生虫病はかゆみはありませんが、動物の死を引き起こす可能性が非常に高いです。重症の場合、猫の体には大規模な脱毛、浮腫、紅斑、皮脂分泌、化膿性皮膚炎などの症状が現れます。患部はかゆくなり、外部リンパ節に病変が見つかることもあります。
耳ダニ: 耳ダニは通常、猫の耳の皮膚に寄生し、寄生虫病を引き起こします。病気の猫は落ち着きがなく、頻繁に頭を振ったり、かゆいところを掻いたりする傾向があります。耳に炎症が起きたり、血腫ができたり、アレルギー反応が起きたりすることもあります。猫の外耳道に厚い黒褐色のかさぶたが見られます。
ノミ: ノミは非常に一般的なタイプの外部寄生虫です。ノミは猫を噛み、血を吸い、毒素を分泌します。この毒素は血液凝固に影響を及ぼし、猫に痒みを引き起こし、猫の通常の生活や休息を妨げ、猫をイライラさせたり落ち着かなくさせます。時間が経つと、健康にも影響が出る可能性があります。
シラミ: シラミは最も一般的な皮膚寄生虫の 1 つです。猫に皮膚炎やかゆみを引き起こす可能性があります。
次に、猫に対する内部寄生虫の害についてお話ししましょう。
回虫:この寄生虫は非常に一般的です。感染すると猫は痩せる一方で腹囲は著しく増加し、発育遅延や嘔吐などの症状が見られます。重症の場合は呼吸困難が起こる可能性があり、子猫が感染した場合は栄養失調で死亡する可能性もあります。
サナダムシ:猫は一般的にサナダムシ感染に非常にかかりやすいです。感染した猫の糞便には脱落した部分が含まれます。これらは通常、黄白色で、ゴマ粒ほどの大きさです。条虫に感染した猫は、食欲不振、便秘と下痢の繰り返し、そして体重の大幅な減少を経験します。
鉤虫:これは比較的よく見られる種類の猫の寄生虫です。感染後の主な症状は、消化器障害、貧血、栄養失調などです。
フィラリア症: 咳、疲労、体重減少、うつ病はフィラリア症に感染した猫によく見られる症状です。猫は怯えたり、気を失ったり、下痢を起こしたりすることもあります。症状が悪化すると、感染症で死亡する可能性もあります。
トリコモナス:トリコモナスに感染した猫の主な症状は、下痢、便の最後に血や粘液が混じること、食欲不振、嘔吐、体重減少です。通常、このような状況が発生した場合、猫はトリコモナスに感染していると最初に判断されますが、猫疫病の可能性も否定できないため、猫の飼い主は早めにペット病院に連れて行き、検査を受けることをお勧めします。
ジアルジア: 実際、ジアルジアに感染した場合の反応は、他の寄生虫に感染した場合の反応とは多少異なります。猫の精神状態や食生活は良いのですが、どうしても体重が増えません。時々下痢をしますが、薬を飲んでから数日間は下痢が続き、さらに数日後にまた下痢をします。
感染初期段階では、猫の精神状態はあまり変化しません。時には疲れてしまったり、食欲が少し落ちてしまったりすることもあるので、飼い主さんに無視されてしまいがちです!急性期に入ると、猫は40℃以上の発熱、食欲不振、憂鬱、体重減少、歩行不安定、転倒しやすいなどの症状が見られ、さらには貧血、視神経粘膜の蒼白、突然の虚脱などの症状も現れます。
猫の駆虫方法は?どのような駆虫薬を使用すればよいですか?
猫の健康に対する寄生虫の脅威がわかったので、駆虫薬で寄生虫を「撃退」しなければなりません。そこで、ダミャオさんは猫の飼い主に以下の駆虫薬も勧めています。免責事項: この推奨はいかなる商業行為も構成するものではありません。これらはすべて、Da Miao が個人的に使用した薬、または周囲の猫の飼い主が使用して承認した薬です。
猫用外用駆虫薬
猫用のフロントライン プラスは、ノミやシラミの感染を効果的に予防し、治療する薬です。生後8週くらいから使えます!
猫用フロントライン プラス スプレーは、ノミ、シラミ、ニキビダニ、耳ダニを予防および治療します。フロントライン プラス スプレーは、点滴薬よりも優れており、生後 2 か月未満の子猫にも使用できます。つまり、猫が生後 2 日以上であれば、この薬を使用できるということです。
バイエルの外用忌避剤としても知られるアドボケイトは、ノミ、耳ダニ、ニキビダニ、疥癬、シラミのほか、回虫、鉤虫、鞭虫、肺虫の幼虫および成虫の治療に使用できます。この薬は生後9ヶ月以上の猫にのみ使用できます。 Iwalker には、異なる体重の猫向けに設計された 2 つのパッケージがあります。 1つは4キログラム未満の猫用、もう1つは4キログラムを超える猫用です。
レボリューションは主に耳ダニ、フィラリア、ノミの治療と予防に使用される薬です。猫がこれを使用するには、少なくとも 8 週間齢である必要があります。この薬は猫の駆虫薬として、生後2ヶ月以上の猫用2.5kg、生後2ヶ月以上の猫用2.6~7.5kg、生後2ヶ月以上の猫用6.8kgの3つの規格に分かれています。猫の飼い主さんは自分の猫の体重に合わせて選べます!
使い方についてお話ししましょう!外付けドライブドラッグドロップの使用方法:
この方法については先ほど説明しました。猫の飼い主さんと一緒に考えてみましょう。まず、猫の首の後ろの肩甲骨の間の毛を手でかき分けて、皮膚を露出させます。次に、猫の皮膚に滴下します。すぐに離さないように注意してください。薬をゆっくりと猫の皮膚に浸透させて、猫の毛を整えてあげましょう。ドロップは他の場所にはドロップできません。首の後ろの肩甲骨の真ん中あたりに落とさなければなりません。
注記!薬を塗った部分を手でマッサージする必要はありません。また、傷ついた皮膚に薬を落とさないでください。使用後72時間以内に猫を入浴させないでください。
外付けドライブ薬剤スプレーの使用方法:
スプレーの使い方は比較的簡単で大まかです。猫の首の後ろをつかんで、顔や尻尾を含む全身にスプレーします。多くの猫が顔にスプレーされることを怖がっている場合は、最初に柔らかい布やティッシュに薬をスプレーしてから、猫の顔を拭くことができます。
内服の駆虫薬については、バイエル社の猫用駆虫薬のみをお勧めします。この薬は、8 種類以上の条虫、回虫、寄生虫、腸内寄生虫をあらゆる段階で駆除できます。通常、バイエル社のエンドルフィンを服用する前には 4 時間の絶食が必要であり、薬を服用してから 1 時間後には食事を続けることができます。ペットの飼い主は薬の指示を厳守しなければなりません!
注意: 薬の効果を確実にするために、ワクチン接種中は猫の駆虫を行わないようにしてください。駆虫とワクチン接種の間には少なくとも 1 週間の間隔をあけてください。
もちろん、駆虫薬を服用すると副作用が出ることもあります。
猫はそれぞれ体格が異なります。猫によっては胃腸の機能がより優れており、駆虫薬を服用しても反応しない場合があります。ただし、胃腸機能が弱い猫の場合、駆虫薬を服用すると軽い嘔吐、下痢、食欲不振などの症状が出ることがあります。実際、これはよくある現象です。心配しないで。通常、1~2日後には状況は改善します。猫の状態を観察できます。長期間改善が見られなかったり、猫が強い反応を示したりする場合は、できるだけ早く治療に送ってください。
では、どのくらいの頻度で猫の駆虫を行うべきでしょうか?
子猫の場合は、生後6週と12週のときに1回ずつ駆虫薬を飲ませるだけで大丈夫です!
生後 6 か月以上の猫は、3 ~ 6 か月ごとに駆虫するだけで済みます。猫が室内のみで飼育されており、生肉、生卵などの食べ物を食べず、キャットフードだけを食べている場合は、6〜12か月に1回駆虫することができます。