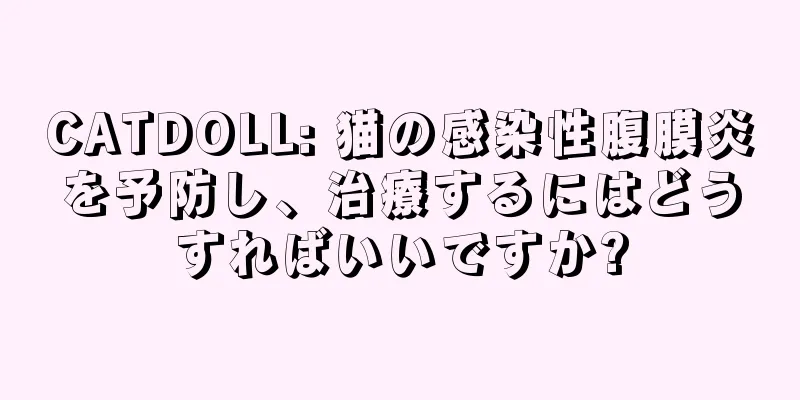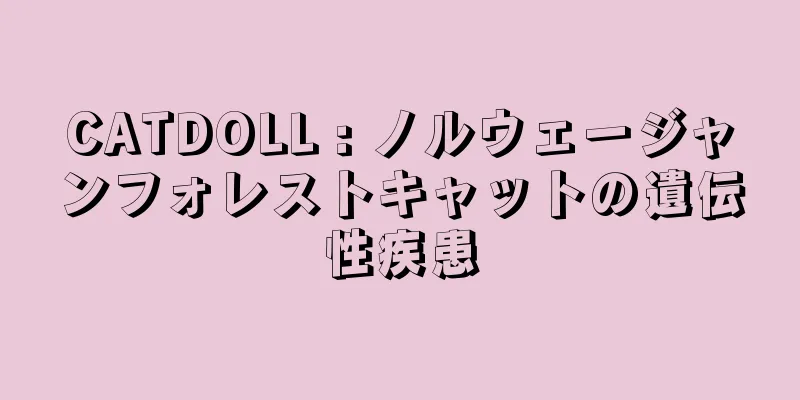この病気は4歳未満の若い成猫、特に群れで飼われている猫によく見られます。病気の経過は突然起こる場合もあれば(子猫に多い)、徐々に進行して数週間続く場合もあります。
初期症状は明らかではなく、食欲不振、気分不良、体重減少、持続的な発熱(39.5~40.6度:夕方に高くなり、夜になると徐々に低下する)などが含まれることがあります。その後の症状は、乾性症状と湿性症状の2種類に明確に分けられます。
ウェットタイプ:
ほとんどの猫は発症後2か月以内に死亡します。
胸部および腹腔内に高タンパク質の滲出液が認められます。
胸水の量に応じて、症状は無症状から息切れや呼吸困難までさまざまです。
進行性で痛みのない腹部の肥大、また雄猫では陰嚢肥大が起こる可能性があります。
嘔吐や下痢が起こる可能性があります。
中度から重度の貧血。
ドライ:
症状には、目の曇り、前房内の膿、縮瞳、視力障害などがあります。
後肢麻痺、けいれん、眼振、性格の変化など、進行性の神経症状を伴う症例もいくつかあります。
肝臓、腎臓、脾臓、肺、大網、リンパ節に結節性病変が現れます。腸間膜リンパ節は腹部の触診で触知できます。
貧血、黄疸。
臨床的には、この病気にかかった猫の死亡率は 95% ですが、食欲旺盛、悪性貧血、白血病、初期の乾性型がないなど、体調が良好な猫の中には、投薬で治療できる猫もいます。状態は 4 週間ごとに再評価し、3 か月後には投与量を徐々に減らしていく必要があります。薬物治療では以下が使用されます。
免疫抑制および抗炎症効果:高用量ステロイド、細胞毒性薬。
二次細菌感染の予防:広域抗生物質
抗ウイルス薬
支持療法: 強制栄養補給(食道または胃チューブによる)、脱水症状を補正するための水分補給、呼吸器症状を緩和するための胸腔穿刺。
諺にあるように、予防は治療に勝ります。この病気を予防するためには、ワクチン接種に加え、生活・飼育環境の管理や血清抗体検査を定期的に行う必要があります。
このワクチンは、16週齢以上の猫に鼻腔内投与され、3~4週間の間隔をあけて2回投与されます。