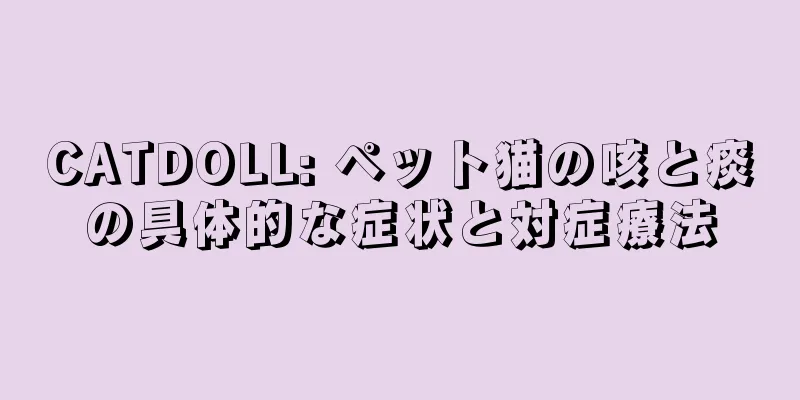血管内皮が損傷すると、治癒するために血小板が損傷部位に付着して凝集し、血管が狭くなり、血管内の血液が詰まります。血管の損傷は、内分泌障害や代謝障害などの慢性的な原因によって引き起こされる場合もあれば、突然の激しい恐怖や何らかの炎症によって引き起こされる場合もあります。術後の合併症によって血栓が発生することもありますが、心臓病を患っている猫では血栓がよく見られるため、日常の食事や治療には注意が必要です。
1. 原因
猫の血栓症は動脈血栓塞栓症によって引き起こされます。動脈血栓塞栓症は通常、左心房または左心室で形成され、血液とともに移動してより小さな動脈で塞栓し、下流の組織への血液の酸素供給を妨げます。塞栓症の 90% 以上は、動脈が 2 本の後ろ足に分岐する大動脈の三分岐部で発生します。塞栓性血栓は鞍型をしているため、鞍型血栓とも呼ばれます。さらに、冠動脈だけでなく、前肢、脳、消化管、肺、腎臓につながる動脈にも血栓が形成されることがあります。
猫の血栓症は通常、肥大型心筋症を示します。猫の血栓症は、腫瘍性疾患(通常は胸部および腹部の腫瘍)や甲状腺機能亢進症によって二次的に発生することもあります。血栓症を引き起こす要因としては、局所的な心内膜の損傷、血液粘度の上昇、左房の拡張などが挙げられます。
2. 疫学
猫の動脈血栓塞栓症の発生率は0.6~0.7%です。罹患猫の約3分の2は雄猫であり、肥大型心筋症の発症率は雄猫で比較的高い。アビシニアン猫は心臓病にかかりやすく、この病気にもかかりやすいです。伝達はどの年齢でも起こり得ますが、中年の猫では発生率が高くなります。これまでのところ、この病気の地理的差異は発見されていない。
臨床症状と診断
鞍型血栓症の典型的な臨床症状としては、両後肢の四肢麻痺、後肢の大腿動脈の拍動消失、末梢四肢および足裏の冷感、足裏および爪床のチアノーゼ(青紫色)などが挙げられます。血栓症の10~12時間後に、局所的な筋肉虚血により脛骨筋と腓腹筋が硬直しますが、この硬直は24~72時間後に緩和します。急性発作を起こした猫は、股関節を曲げたり伸ばしたりすることで後ろ足を引っ込めることはできますが、足首を曲げたり伸ばしたりすることができません。症状は常に片側の方がもう片側よりもひどくなります。ほとんどの猫は脱水症状と低体温に陥り、塞栓が不完全な場合には間欠性跛行のみを示すことがありますが、後になってより重篤な塞栓が発症することがよくあります。
感染した猫は、一般的に、激しい痛み(血液灌流不足による筋肉壊死に起因する)、喘ぎ(痛みによる急速な呼吸)、低体温(ショックに起因する)、血糖値の上昇(ストレスに起因する)、クレアチンキナーゼの上昇(血液灌流不足による損傷に起因する)、高窒素血症(血液灌流不足に起因する腎臓指標の上昇)などの症状を示します。心臓の聴診では、疾走感、心雑音、不整脈などが明らかになることがあります。
片側の上腕動脈血栓症(通常は右前肢)により単麻痺が起こることがあります。体の他の部位で塞栓症が発生すると、腸間膜動脈塞栓症による血便や腎梗塞による高窒素血症など、関連臓器の虚血や壊死による同様の症状が現れることがあります。
基本的な診断は、臨床症状と胸部X線、心電図、心エコー検査、生化学検査、尿分析を組み合わせて行われます。猫では血栓症後、クレアチンホスホキナーゼが急速に増加し、尿素窒素/クレアチニン比、血清アラニンアミノトランスフェラーゼALT、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼASTは血栓症後12時間で増加し、36時間後にピークに達します。高血糖、低カルシウム血症、分裂・帯状白血球の増加、凝固異常などが起こることがあります。急性高カリウム血症は、血栓による下流骨格筋の再灌流障害の結果として発生する可能性があります。食欲減退や利尿剤の使用により、低カリウム血症が起こる可能性があります。心エコー検査では心臓や血管内の血栓を検出することができます。左心房と左心室の特発性高エコー(「煙のような」)外観は、血栓症の前兆である血流閉塞に関連しています。条件が許せば、シンチグラフィー、磁気共鳴画像法、CT、血管造影検査も診断の補助として使用できます。
IV.処理
同時発生しているうっ血性心不全と重度の不整脈をコントロールします。これにはフロセミド、酸素、ACEI、栄養補助食品などの投与が含まれます。
1. 支持療法:
脱水症状の補正、酸・塩基・電解質バランスの調整、保温、栄養補給。食欲不振の猫には、栄養補給のために経鼻胃管を挿入することができます。猫は回復期に自傷行為としてよく見られるため、壊死した手足の末端を過度に舐めたり噛んだりすることも避けるべきです。血栓ができた手足に静脈カテーテルを挿入することは避けてください。
2. 痛みをコントロールする:
塞栓後 24 時間以内に激しい痛みが生じますが、その後急速に治まります。アスピリン(25 mg/kg、2日に1回)は鎮痛剤であると同時に血小板凝集抑制剤でもあります。副作用は食欲不振と嘔吐です。フェンタニル鎮痛パッチまたはヒドロモルフォン(0.05~0.1 mg/kg)は中等度から重度の痛みのコントロールに使用でき、ブトルファノール(0.2~0.4 mg/kg)は軽度から中等度の痛みのコントロールに使用できます。後者の 2 つの薬剤は、6 ~ 8 時間ごとに 1 回、または必要に応じて 4 時間ごとに 1 回、皮下、筋肉内、または静脈内に投与できます。
この病気の原因にかかわらず、心不全や呼吸不全を伴うことがよくあります。したがって、初期診断時には、強心薬と利尿薬による治療を直ちに行う必要があり、細菌性心内膜炎が原因の場合は抗生物質による治療も行う必要があります。
3. 抗凝固剤(ヘパリン 500~800 単位/動物、静脈内注射。追加投与は凝固時間に基づいて 3~8 時間ごとに皮下注射または静脈内点滴)および血栓溶解剤(ウロキナーゼ、3000~6000 単位/動物、静脈内点滴)を投与します。薬物治療が行われている間に、できるだけ早く血栓除去術を行う必要があります。ほとんどの手術は血管造影ガイド下で行われるため、麻酔はできるだけ軽く維持する必要があります(たとえば、猫の場合は0.1%の少量を静脈内投与し、筋弛緩剤の塩化サクシニルコリンを0.2 mg/kg静脈内注射します)。
4. 外腸骨動脈分岐部の鞍型血栓の場合は、腹部正中線に沿って腹腔を開き、動脈を慎重に剥離し、塞栓部位を止血鉗子で前後から挟み、近位端を小さく切開して血栓を絞り出します。ときには、心臓から遠く離れた末梢動脈に血栓が形成されることもあります。形成された血栓は細くて長いので、取り除くときに壊さないように注意してください。必要であれば、カテーテルを大腿部の動脈に挿入して血栓の近くに置き、陽圧を加えて血栓を洗い流すこともできます。血管を縫合する前に、左右の末梢血管にヘパリンと生理食塩水を注入しました。縫うときは針穴を近づけてください。
5. 手術後は体温維持、栄養補給、持続的な酸素吸入に注意してください。