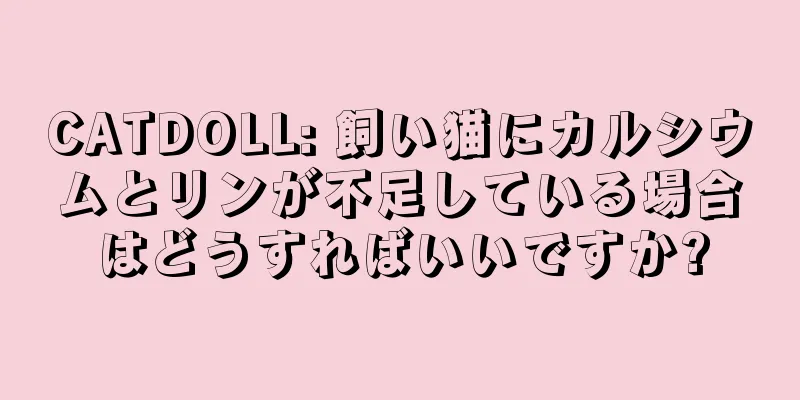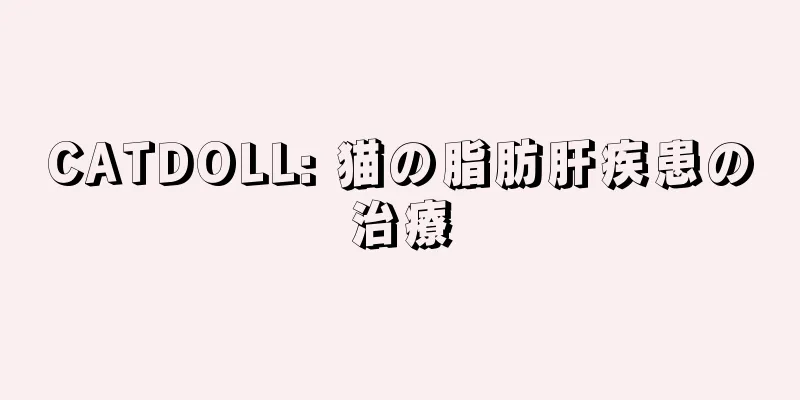カルシウムとリンは体にとって極めて重要な微量元素であり、主に無機塩の形で体内に蓄えられています。猫に餌を与える際には、さまざまな栄養素を考慮する必要があり、当然のことながらカルシウムやリンの補給にも注意しなければなりません。猫はカルシウムやリンが不足すると骨粗しょう症やくる病になるという話をよく聞きます。では、カルシウムとリンの代謝は体にとってどのような意味を持つのでしょうか?
体内のカルシウムとリンの化合物は、体内の総ミネラルの65〜70%を占め、主に骨を構成しており、そのうち骨のカルシウムは体内の総カルシウムの90%を占め、骨のリンは体の総リンの85%を占めています。残りのカルシウムは血液、リンパ、組織中に存在し、残りのリンは様々な臓器や組織中に存在し、主にリンタンパク質、核タンパク質、リン脂質、クレアチンリン酸、アデノシン三リン酸などを形成して細胞内に蓄えられます。
カルシウムとリンの主な機能は次のとおりです。
1. 体を構成する支持組織 - 骨。骨は代謝が活発な組織であり、成長期の動物でも成体の動物でも常に再生され修復されています。
2. カルシウムは筋肉内の多くの酵素の活性化因子および阻害因子であり、体内の代謝に関係しています。
3. カルシウムは神経や筋肉の興奮性を抑制する可能性があります。カルシウム濃度が正常値より低い場合、節前神経線維と節後神経線維の興奮性が高まり、重篤な場合にはけいれんが発生します。カルシウム濃度が正常値より高くなると、筋肉や神経線維の興奮性が低下します。
4. リンは骨の主成分であるだけでなく、リボ核酸やデオキシリボ核酸の主成分でもあります。
5. リンはクレアチンリン酸とアデノシン三リン酸の成分です。これら2つの物質はエネルギー貯蔵物質であり、筋肉の収縮と代謝に密接に関係しています。
カルシウムとリンの吸収と排泄:
体内のカルシウムは主に食物から摂取され、そのほとんどは小腸の上部で吸収されます。吸収されるカルシウムの量は、腸内のカルシウム濃度、体の必要量、腸内の pH 値に関係します。腸内の酸性度が上昇すると、カルシウム塩の溶解度が高まり、吸収が増加します。腸内にアルカリ性物質が存在すると、不溶性のカルシウム石鹸が形成され、カルシウムの吸収が低下します。成人はタンパク質を豊富に含む食品を食べるとカルシウムの吸収が増加します。吸収されるカルシウムの量は体の必要に応じて調整されます。カルシウムが不足すると腸からのカルシウムの吸収率が上がり、体内のカルシウムが多すぎると吸収率は下がります。摂取したカルシウムの80%は便を通して排泄され、20%は腎臓を通して排泄されます。糸球体から濾過されたカルシウムの98%は再吸収されるため、尿中に排泄される量は多くありません。尿中に排出されるカルシウムの量は、以下の要因によって影響を受けます。
①カルシウム摂取②腎臓の酸塩基調節機能③副甲状腺ホルモンの分泌。副甲状腺ホルモンは、腎尿細管によるカルシウムの再吸収を促進し、リンの再吸収を阻害するため、血中カルシウム濃度を上昇させ、血中リン濃度を低下させます。
リンは小腸の上部でも吸収されます。腸内の酸性度が上昇すると、リン酸の吸収が増加します。カルシウム、マグネシウム、鉄などのイオンのリン酸が不溶性の塩に結合すると、吸収されにくくなります。そのため、血中カルシウムが上昇すると腸内のカルシウム濃度も上昇し、リンの吸収を妨げます。摂取されたリンは糞便と尿中に排泄され、後者が60%を占めます。血漿中のカルシウムとリンの濃度の調節。毎日のカルシウムとリンの摂取と排泄は動的なバランスを保ち、血中のカルシウムとリンのレベルは比較的安定したままです。これは、副甲状腺ホルモン、カルシトニン、1,25-ジヒドロキシコレカルシフェロール [1,25-(OH)2-D3] の 3 つのホルモンの相乗作用に依存します。
猫が十分なカルシウムとリンを摂取しないと、カルシウム・リン代謝疾患を発症します。猫のカルシウム・リン代謝疾患の診断は、通常、病歴と臨床症状に基づいて予備的に決定できます。検査室では血中カルシウム濃度と血中リン濃度を検査します。機器に問題がなければ、テスト結果の精度は 99% になります。早期治療を重視すべきです。治療が早ければ早いほど、回復が早くなり、後遺症も少なくなります。ビタミン D の投与に加えて、適切な給餌と、特に朝と夕方の動物の運動量の増加に特別な注意を払う必要があります。くる病にかかっている猫は、より多くの日光を浴び、ビタミン D を補給することで、病気の回復に効果があります。
治療法としては、1日1回5~10mlのタラ肝油を経口摂取することなどが挙げられます。または、ビタミンD3注射を体重1kgあたり1500~3000IU、1回筋肉内注射し、半月ごとに繰り返します。